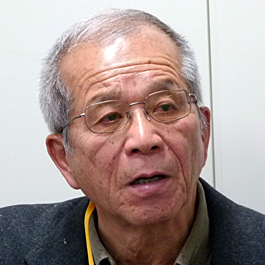《『PHPビジネスレビュー松下幸之助塾』 2014年5・6月号Vol.17[特集]実践! 自主責任経営 より》
――松下幸之助が「理想とした組織」と「歴史の現実」

松下幸之助の自主責任経営と言えば、連想されるのが事業部制。製品別に分かれた各事業部が開発から生産、販売、収支管理までを一貫して行い、いっさいの責任を持って経営に当たるシステムだ。松下幸之助は1933(昭和8)年、この事業部制を採用し、松下電器(現パナソニック)の業容は拡大を遂げた。ところがその後、戦争の時代を境に、当初とは異なる構造の事業部制が展開されていく。その歴史的展開と背景について、松下電器の勤務経験があり、「フロー理論」の観点から松下幸之助を研究してきた経営学者の大森弘氏に語ってもらった。
<聞き手:川上恒雄(PHP研究所松下理念研究部主席研究員)>
なぜ、製販一体の組織に?
――昨年、パナソニックで事業部制が復活し、話題になりました。松下幸之助の研究者として、どんな印象を持たれましたか。
現在のパナソニックの経営についてはよく存じあげていないのですが、事業部制について言うと、そのことばだけが独り歩きしているように思われてなりません。たとえば、事業部制とは独立採算制のことだとする見方があります。たしかにそのような面もあるのですが、松下幸之助の考え方に照らせば、独立採算が事業部制のすべてではない。
松下電器時代の組織の変遷をたどると、戦前、終戦後、高度経済成長期と時代が下るにつれ、大きな変化がみられます。つまり、同じ「事業部制」という表現を用いていても、そのかたちは1つではありませんでした。問題は、松下幸之助の意図した事業部制だったかどうかということです。
――松下電器は1933(昭和8)年に事業部制を採用しましたが、その松下幸之助の意図したものとは何だったとお考えですか。
一般論としては、松下電器の業容拡大に伴い、病気がちな松下幸之助が経営のすべてをみるには大きくなりすぎたため、製品別の事業部に分け、そのおのおのの経営を部下に任せたということがあげられるでしょう。また、恐慌を経験したあとでもあることから、リスク分散のために事業部に分割したのかもしれません。
しかし、私はもっと本質的な理由があったと考えています。松下幸之助の真意をつかむには、「モノをつくる前にヒトをつくる」という基本的な考え方に立ち返る必要がある。ヒト、モノ、カネという経営資源について、松下幸之助の場合、インプットがヒト、スループットがモノ、アウトプットがカネ、という関係にあることから、事業部制を解釈する前提として、モノづくりとかカネづくりとか言う前に、ヒトづくりが先にくることを頭に入れておくべきです。
具体的には、1927(昭和2)年に創設した電熱部の経営を当初お米屋さんの友人に任せて失敗したことが、事業部制採用の遠因ではないかとみています。経営は副業でやるべきではなく、責任を持って真剣に打ち込まねばならないことを松下幸之助はその失敗から学びました。そこで、部下が経営に集中できるような組織構造を考えたのでしょう。
その構造を具体的に説明すると、当初は事業部が3つあり、第一がラジオ部門、第二がランプ・乾電池部門、第三が配線器具・合成樹脂・電熱器部門でした。第一事業部のみが製造と販売の双方の機能を備えていましたが、1934(昭和9)年、電熱器部門が独立して第四事業部になるとともに、全事業部が製販一体のシステムに移行します。組織図からはよく分かりませんが、各事業部の傘下に工場があり、営業所である各支店や出張所の内部が製品別に分かれていて、各事業部と直結していたようです。
製販一体にすることにより独立採算の経営を促し、自主責任意識を高めようとしたのでしょう。また、製品別に事業部に分けることで、社員一人ひとりが担当の仕事に集中できるようにしたのだと私は考えています。仕事に熱中できるとともに経営意識を育めるような組織にすることが、松下幸之助のほんとうの狙いだったのではないでしょうか。
「事業部的思想」の時代
――その後の1935(昭和10)年、分社制に移行しました。このとき松下幸之助は、事業部制も分社制も実質は変わらないと述べていたようですが、分社制にした意図は何かあったとお考えですか。
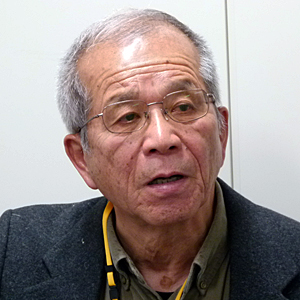 松下幸之助が何の意図もなく、組織を変えるはずがありません。社員を安心させるために、大きな変化がないことを強調したのでしょう。
松下幸之助が何の意図もなく、組織を変えるはずがありません。社員を安心させるために、大きな変化がないことを強調したのでしょう。
分社制では、持ち株会社である本社の松下電器産業株式会社のもとに、製品別の株式会社が置かれるようになりました。営業部門である貿易や直売なども分社化され、総務部や研究部以外はすべて分社に権限を与えています。分社の社長は本社社長の松下幸之助が兼務したものの、実質的な経営は専務をはじめ本社の役員が当たったようです。
企画本部で私の上司だった藤尾津与次常務(当時、のち専務)は、この戦前の分社制について、「事業部の自主性というものを、さらに強く植えつけるために、会社という法的な形式づけをした」と述べたうえで、「事業部的思想の一番浸透した」組織だったと回顧しています(『社史資料 №7』参照)。つまり、分社制は、事業部制の進化したかたちだったということです。
重要なのは、自主性を重んじるこの「事業部的思想」であって、事業部制とか分社制とかいうかたちや名称ではありません。戦前の分社制には、まさにその思想が息づいていたと言えるでしょう。
――しかし、分社制は長くは続きませんでした。
戦争になって統制経済の時代に入ると、市場で資材を調達し、製品を販売することがそもそもできない、つまり製販一体での経営が困難になる。その結果、1944(昭和19)年、分社は解散され、1つの会社に戻りました。製品別の製造所と地域別の営業所を別に設けていることから、製造と販売が分離したことが分かります。終戦後もしばらくは厳しい経営環境にありましたから、基本的には戦時中の組織構造を継続したようです。
戦争という特殊な時代背景を考えると、こうした組織構造の改編は理解できるのですが、注目すべきは、その戦時組織の性質が、一時的なものにとどまらなかったということです。
本部制と製販分離の問題
――戦後は、事業部制が復活したことになっていますが……。
現実は、そんなに単純ではなかった。先に申しあげたように、名称は事業部制でも、その中身はいろいろです。戦前の事業部制や分社制のような組織構造がそのまま復活したわけではありませんでした。
☆本サイトの記事は、雑誌掲載記事の冒頭部分を抜粋したものです。
<掲載誌紹介>
 2014年5・6月号Vol.17
2014年5・6月号Vol.17
5・6月号の特集は「実践! 自主責任経営」
「自主責任経営」とは、“企業の経営者、責任者はもとより、社員の一人ひとりが自主的にそれぞれの責任を自覚して、意欲的に仕事に取り組む経営”のことであり、松下幸之助はこの考え方を非常に重視した。そしてこれを実現する制度として「事業部制」を取り入れるとともに、「社員稼業」という考え方を説いて社員個人個人に対しても自主責任経営を求めた。
本特集では、現在活躍する経営者の試行や実践をとおして自主責任経営の意義を探るとともに、松下幸之助の事業部制についても考察する。
そのほか、パナソニック会長・長榮周作氏がみずからを成長させてきた精神について語ったインタビューや、伊藤雅俊氏(セブン&アイ・ホールディングス名誉会長)、佐々木常夫氏(東レ経営研究所前社長)、宇治原史規氏(お笑い芸人)の3人が語る「松下幸之助と私」も、ぜひお読みいただきたい。