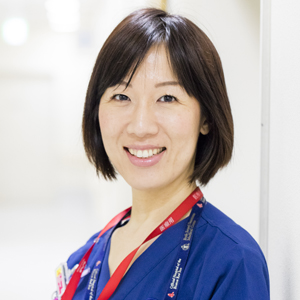救急医がすべきこと、すべきでないこと―「命」の現場での判断
2016年03月04日 公開 2024年12月16日 更新

『救急医 驚異の判断力』(PHP研究所刊)より
そのとき医者、患者、家族は何を決断するのか
福知山線脱線事故
「患者さんやご家族の憤りとは、こんなにやり場のないものなのか」
医者として、わかっていたつもりのことを、あらためて思い知らされた事故でした。
2005年4月25日9時18分、福知山線脱線事故が発生。
救命救急センターに第一報が届くと、その後10~15分おきに次々と救急車が到着。合計8人の患者さんが運び込まれました。
私が担当したのは、高齢の女性です。肋骨があちこち折れて、自力では呼吸ができない状態。意識もありません。いうまでもなく重症ですが「……何で、こんな目に遭わなきゃいけないんだ」という感情を露わにしていたのは、患者さんではなく、患者さんに付きそうご家族のほうでした。事故を天災だと諦めることができず、かといって人災であるという確証はない。彼らは、やり場のない怒りを胸のうちに押し込めていました。
「病院に運ばれてくる前のことには全く踏み込まない」――それが事件や事故の被害者を治療する医者の基本的なポリシーです。今ここから治療が始まるのであって、それ以前のことは介入しないと割り切る。その割り切りが、ベスト・パフォーマンスを生み出すのだと信じてもいます。
しかしこのときは、「関係せざるを得ない」と思うくらいの怒りが、ご家族から私にも伝わってきました。
「なんで、こんな目に遭わないといけないんですか」
「これで障害が残ったら、どうするんですか」
「なぜ、こんなことに……」
けがの治療よりも、そんなご家族の訴えを受け止めるほうが、はるかに難しいことでした。病状を心配する気持ちはもちろんですが、「事故にあった」ことの不条理に苦しんでおられるように見えたからです。
それほどにご家族が憤っていたのは、もうひとつ理由があります。JRの職員の方が毎日24時間、病院の待合室に詰めていたことです。
ご家族の目に映る彼らは、事故の「加害者」。直接の加害者ではないことがわかっていても、ご家族はそう思わないではいられません。すると、患者さんの症状や今後を心配するあまり、「あいつらが……」という思いで一杯になってしまうのです。
治療について、「いまはこういう状態ですが、もしかしたら人工呼吸の管を抜けないかもしれない。高齢ですので、急変するリスクもある」などとお話をしたときのご家族が見せた表情は、今でも忘れられません。怒りを超えた憎悪という感情を隠し切れないご家族……。「加害者」に殴りかかるわけにもいかないと、感情を押し殺しているご家族……。
そんなご家族が被害者の数だけいらっしゃるのです。面会のたびに被害者のご家族同士の結束が固くなり、憎悪も募っていく。私が直接担当した患者さんは幸い無事に退院することができました。
次のページ
「もしも、○○だったら」というご家族の願いと医者の答え