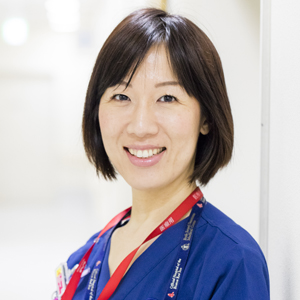救急医がすべきこと、すべきでないこと―「命」の現場での判断
2016年03月04日 公開 2024年12月16日 更新

「もしも、○○だったら」というご家族の願いと医者の答え
救急の場にいるとしばしば遭遇する、極限状態における人間の感情。
病院では時に、加害者と被害者が同じ空間を共有することになります。自分や自分の家族を深く傷つけた相手が、すぐ隣にいるとき、人はどう振る舞えばいいのでしょう。心配して見舞いにきた加害者に罵声を浴びせる被害者のご家族、殴り掛かる被害者の方……。
私たち医者にはどうすることもできず、見守るしかありません。こちらから双方の間に踏み込んでいき、ケアできる類のものではないのです。人の気持ちは本当に難しく、医者は無力です。
「もうちょっと、事故の形が違っていたら、こんなふうにならなかったんでしょうか」
「向こうがスピードを出していたから、こうなったんですか」
ご家族からそういって詰め寄られることも少なくありません。
ご家族がどんな答えを欲しているのか、痛いほどわかります。
しかし、医者には決して答えられない質問です。医者は真実を知りうる立場にはないからです。言ってほしいことを言わないために、ご家族が私に不信感を持ち、治療に支障を来すことも考えられますが、それでもお答えはできないのです。
「これほどの事故なら、頭も打っていてもおかしくなかったですね。でも今回、頭は大丈夫でしたよね」
私が話せるのは、こんな程度のこと。やっていることは話のすり替えですから、自分でも「ズルイ」と感じています。
でも、私は嘘を言っているわけではありません。
正解のわからない事故の原因を追求することに時間を費やすよりも、命が助かったことの幸運を喜ぶことに気持ちを向けてもらえたら、と思うからこそ、こう言わざるをえないのです。
ご家族は事故の否定的な側面に囚われ、苦しんでいらっしゃいます。対して私は、ほんのわずかでも残っている、肯定的な側面を指摘する、というだけ。起こってしまった事故はもう取り返しがつきません、時計の針を巻き戻すこともできません。そのとき何があったのか、真実を語れる人もいないのです。
そのような状況下でも、希望を持っていただきたいと私は思います。そして事実、希望はあるのです。
「現場で亡くなっていてもおかしくない状況でしたよ」
「重症ですけど、助かる見込みもあります、決して諦めていません」
「命がある」ことの価値に、ほんの少しでもまなざしを向けていただきたい。そう願いながらお話しするようにしています。
ここでは、医者と患者の間に、明確な一線を引いています。そうでもしないと、私たち救急医も精神的に持ちこたえられないからです。「患者さんの命を救いたい」と願いながら、現実には救えない命がある。それだけでも辛いのに、患者さんやご家族に感情移入しすぎると、いつか燃え尽きてしまうことでしょう。
「自分が担当医じゃなかったら、救えたかもしれない」
そう言って救急を辞めていった先生がいます。自分のことを疑った瞬間に「もう辞めよう」と思ったそうです。医者は自分のことを疑ってはいけない、希望を持つことをやめてはいけない。それができなくなったときが、私が医者を辞めるときです。