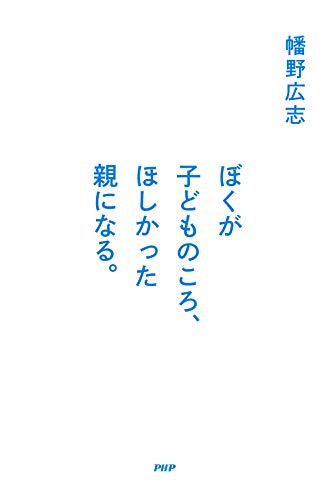西洋医学の常識を覆す「あまりに美しい死にざま」
夫が旅立った直後、私は彼が言い残してくれたとおりに、淡々とやるべきことを進めました。「夫の胸にすがって、いつまでも泣き続ける」というようなことはありませんでした。
経験された方ならわかっていただけると思いますが、残された側には、やるべきことがけっこうたくさんあるのです。彼は「何も必要ない」というような無頼な人でしたから、私がやることは普通よりも少なかったと思います。それでもいろいろな手続きに気ぜわしいものでした。
「戒名はいらないから、実名で墓に入れてほしい」
「お葬式はいらない」
「仕事の関係者にも一切知らせなくてよい」
「お坊さんはいらない」等々……。
ただ、母に「家運が下がる」と猛反対をされ、お坊さんは呼ぶことにしました。
また担当の在宅医には、報告の電話をすぐにしたのですが、来てくれたのは午後2時ごろ。つまり死後12時間経ってからの到着でした。私たちはその間、夫を着替えさせ、夏場だったので葬儀屋さんにドライアイスで冷やしてもらいました。
遺体の処置といえば、それだけ。
なぜなら夫の体はむくみとは無縁で、「ほどよくドライ」に枯れていたからです。病棟で遺体に対して行われるいわゆる「エンゼルケア」の類は、まったく無用でした。
それに生前は、終末期医療にはつきものの「痰(たん)」に悩まされることもありませんでした。
点滴を続ける間は、余分な水分が痰として現れるため、常に口内除去を行わなければいけません。
けれど、必要なとき以外に水分をとらなかった夫の場合は、一時期をのぞいて、痰が口にたまったり、のどで絡まるといったことがありませんでした。
ですから、私の心配をよそに、呼吸はいつもおだやかそのもの。はじめは本当に驚いたものです。
無理やり水を飲ませたり、過剰な点滴をしたり……。それらがいかに体に不必要なものか、夫は身をもって教えてくれました。
私はそれまで、看護師として何百人もの看取りに立ち会ってきましたが、これほど美しい死にざまは、病院で見たことがありませんでした。
じつは、極力医療の力を借りず「治療をしない患者」を看取った経験自体が、初めてだったのです。
「ほどよくドライ」な夫の遺体は、〝西洋医学漬け〟だった私の価値観をがらりと変えてくれました。
とはいえ、誤解のないよう申し添えておきたいのですが……。
「何が何でも自然死を推奨したい!」というわけでは、けっしてありません。
自然死を、すべての人に強要したいわけでもありません。
あくまでも、本人の望む「逝き方」がベスト。
そんな思いをますます強くしています。
在宅介護は「生きている」と「死んでいる」の境界をなくす
しかし、死とは不思議なものです。
そのような旅立ちまでの助走期間をわが家でずっとすごしていたため、私たちのショックは「少なかった」というか、「亡くなった」と頭でわかってはいても「普段」の暮らしがまだ続いている感じがしてなりませんでした。
「夫が生きていること」と、「夫が死んでいること」の差がほとんどない、と言えばよいでしょうか。
在宅で介護し、看取りまで行うことは、死生観に大きな影響を与えるのだと、あらためて気づかされました。
率直なところをお話しさせてもらうと、映画や小説でよくあるセリフのように「もう一度会いたい」などという思いは、あまりありません。なぜなら、私たち親子の周りにいつもフワフワといてくれている感じがするからです。亡くなってから数年経った今でも、です。
とはいえ、彼は「死んで仏様になった」というような立派なイメージでもありません。人の体の形をした〝入れ物〟がなくなっただけで、そこらへんに粒となって漂っている気がするのです。
たとえば今でも、夜になると、家がガタガタ、ギシギシと鳴ることがあります。
木造の古い家だから、ガタがきているだけでしょうが、物音がする度、反射的に「あ、夫が来ている」と思ってしまうのです。その度に親子で「お父さんだねぇ」と言い合うのですが、怖がるわけでもなく、とくに喜ぶわけでもない。
自然に「今日も来ているねぇ」と温かい気持ちで受け止められるのは、やはり在宅療養で旅立ちに伴走したからと思えてなりません。また、私の中に実感として夫のぬくもりが残っているからでもあるでしょう。
在宅療養中、夫が私の手をそっとにぎってくれたことがあります。彼は普段、そんなことをする性格ではありませんでしたが……。
その感触は、私の中にいまだに残っていますし、そのときの情景も私の記憶に鮮やかにあります。
今後、私がどれだけ年をとっても、どれだけつらい目にあっても、その感触と記憶は、誰かに奪われることはないでしょうし、色あせることもありません。
これからも、夫の手のぬくもりの感触と記憶をときどき味わいながら、自分の人生を歩んでいければ、それ以上の幸せはないと思っています。