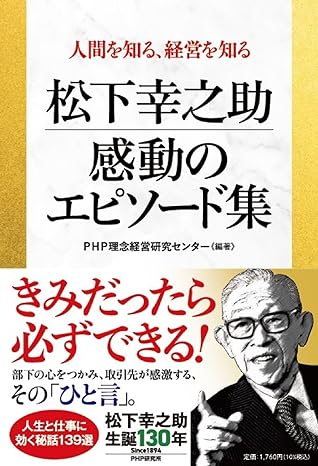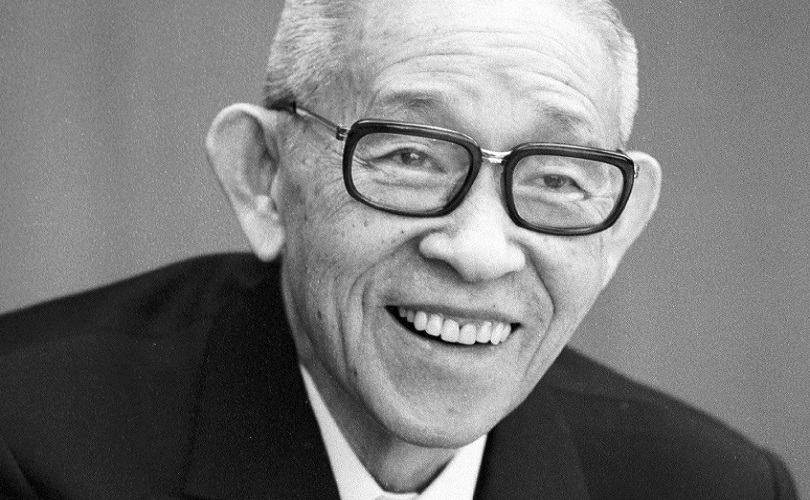会社は公器...松下幸之助が“都心の人口集中”を予測して下した決断
2024年06月14日 公開 2024年12月16日 更新

一代で世界的企業を築き上げ、"経営の神様"と呼ばれた松下幸之助だが、成功の陰には数々の感動的なエピソードがあった――。「安く買ってはいけない」「松下電器というのは社会の公器や」...。幸之助が経営者として大切にしていたこととは? 4つのエピソードを紹介する。
※本稿は、PHP理念経営研究センター編著「松下幸之助 感動のエピソード集」(PHP研究所)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
安く買ってはいけない
松下電器がソケットはつくっていたが、まだその材料であるベークライトをつくっていなかったころのことである。松下電器としては、ベークライト工場がほしいと常々考えていた。
そんなあるとき、そのどちらもつくっている電器会社がゆきづまり、その経営を引き受けてくれないかという話が、当の電器会社から松下電器に持ち込まれた。松下電器としては好都合であった。かねがねほしいと思っていたベークライト工場が、向こうから飛び込んできたのである。さっそく買収することを決定し、具体的な交渉に入った。
そのときに幸之助が指示したことは、「安く買ってはいけない」ということだった。相手は倒産しかかっており、弱い立場にある。相当安く買いたたいたとしても、相手も世間も納得するであろう。
しかし、幸之助はこう考えた。
"松下電器がベークライト工場をつくるのであれば、みずからその研究をし、開発をしなければならない。そうなると、多くの資金が必要になる。ところが幸いにして、ベークライト工場を買収してほしいという話が持ち込まれた。その工場は松下電器が必要とする、いわば値打ちのあるものだ。その値打ちで買おう"
その考えのとおり、幸之助はその工場を値切ることをせず、相場で買った。
重役に会わなかった話
松下電器が多少大きくなった昭和初期のことである。新しく事業を拡張するのに200万円必要になった。当時では相当の金である。それまでにも10万、20万という金を銀行から借りていたが、そのときも同様に幸之助は、銀行の支店長を訪ね、その話をした。
「それは結構です。松下さんの今までを見ていると、ほとんど言われたことと違いがない。だから今度も、私はお貸ししたいと思うのですが、しかし、金額が金額です。で、この際、私が紹介しますから一度うちの重役に会って話をしてくださいませんか」
まだ規模の小さい町工場の経営者にとって、銀行の重役に紹介してもらえるということは名誉なことでもあった。しかし、幸之助は丁重にそれを辞退した。
「なぜですか」
「重役さんにご紹介いただくのはまことに光栄なことですが、お会いしたとしてもあなたに申しあげたことと同じことしかお話しできませんので......。重役さんにはあなたからお伝えください」
そう言われて、支店長は困ったが、最後には、
「それでは私から話してみましょう」
ということになった。
そして幸之助は、結局、申し込んだ200万円を借りることができたのである。なぜ、重役に会わなかったのか。その理由を幸之助は、著書『経済談義』の中でこう書いている。
「これは自分自身の仕事をしているのではない、私はそう考えた。社会のためにやっている仕事である。つまり世の中が進歩発展してきて、こういう新しい仕事が必要になり、求められるようになってきた。その求めに応じて自分はやっているのだ。だから、そのために正当なというか必要な努力は大いにやるし、またやらなくてはならない。
しかし、正当以上の、いわば卑屈な努力までする必要はない。そういう考えをハラの底に持っていたのである。自分はこの仕事が社会に必要だと思い、また自分にはこれをやっていける力もあると思うけれども、銀行が貸してくれないのなら、それをやめて、やらないだけだ、そういった気持ちでいた。
だからせっかくの支店長の好意ではあったが『同じことをいうのに重役の人に会う必要はありません。それでよかったら貸してください。貸していただけなければ仕事をのばすだけですからけっこうです』といったわけである」
この話は、幸之助があるとき、「いちばん素直な心だったと思うことは?」と問われて披露したエピソードでもある。
経営指導料
松下電器がオランダのフィリップス社と技術提携した際、一つの大きな問題となったのは技術援助料の高さであった。フィリップス社は7パーセントを要求してきた。
「アメリカの企業は3パーセントなのに、なぜお宅は7パーセントもの技術援助料を要求するのだ。ちょっと高すぎるのではないか」
フィリップス社はそれに答えて、
「わが社と提携すれば必ず成功する。それだけの責任を持つし、過去の実績を見ても、それはわかるだろう」
と言う。たいへんな自信である。しかし、交渉を進めるうちに、技術援助料は4.5パーセントまで譲歩してくれた。しかし、それでもまだ高い。
幸之助は、なぜフィリップス社の技術援助料がそんなにも高いのか、静かに考えてみた。
"アメリカの技術も、フィリップス社の技術も、技術それ自体はそんなに大きな差があるわけではなかろう。にもかかわらず、それだけの値段の差があるというのは、それは技術以外の面、すなわちその技術をいかにして活用し成果を上げていくか、そうした面に違いがあるのだろう。しかし、待てよ。それならば......"
幸之助はあることに思い至った。
"技術を導入する側によっても、その成功の度合が異なるはずではないか。言ってみれば、学校だって、いくら先生が上手に教えても、生徒によっては十分にそれが生かせない生徒もあれば、反対に十二分に理解し体得する生徒もいるだろう。手のかかる生徒もいれば、手のかからない生徒もいるわけだ。そう考えると、フィリップス社の言い分は、先生がいいから7パーセントだと言っているのと同じだ。それは生徒の側を無視した考え方ではないか!"
そこで幸之助は、このような意向を伝えた。
「フィリップス社が松下電器と契約したならば、フィリップス社がこれまでに契約したどの会社よりも大きな成功を収めることができる。他の会社との場合を100とするならば、松下電器とならば300の成功を収めることができるだろう。
松下電器の経営にはそれだけの価値があるのだ。だから松下電器の経営の価値に対してフィリップス社は経営指導料として3パーセント、松下電器はフィリップス社に対し技術援助料4.5パーセントを支払うとしてはどうだろうか」
フィリップス社側は驚いた。
「いまだかつてわれわれはそんな経営指導料などというものを払ったことはない。そんなことを耳にするのは初めてだ」
双方いろいろと意見を述べ合った。しかし、松下側が熱心に説いていくうちに、やがて理解も納得も得られ、幸之助の提案どおり技術提携の話はまとまったのである。
*幸之助は常々、とらわれない素直な心で物事の本質をつかむことの大切さを訴えていたが、この契約の経緯も"何が正しいのか"を追求したゆえの結果とも言える。
会社は公器や
昭和30(1955)年のこと、ある中堅幹部が幸之助から、当時松下電器が福岡市をはじめ各方面から強い要請を受けていた九州への工場進出の是非について意見を求められた。彼は、自分の思うとおり、率直に答えた。
「私は不賛成です。いろんな面で不利だと思います」
彼があげる不利な理由をいちいちうなずきながら聞いてから幸之助は言った。
「きみもそう思うか。みんなもそう言っとる。でもな、わしは引き受けることに決めたんや。というのはきみな、九州の人たちがここまで熱心に言ってくれるのに断わることはないとわしは思うんや。
松下電器というのは社会の公器や。貢献する道はいろいろある。けど、わしが考えるに、おそらく今後の日本の社会には、過密過疎という現象が起きるにちがいない。東京と大阪が極度に肥大をして、郡部がだんだんと過疎化していく。
今、九州の人たちがいちばん悩んでいるのはそういうことやろう。職がないから人が出ていくのであり、人口が減少したり、職場に定着しないことが地域社会としての大きな問題になっている。
松下電器に『やってくれ』と言うのは、いろいろ世の中を見わたしてみて、松下電器という会社がいちばん適当だと皆さんが考えて、そうおっしゃってくださるのや。その好意にこたえるのがわれわれの義務やないか。ここでわれわれが一所懸命やって、九州経済あるいは九州地域全体に貢献することは、すなわち、日本に貢献することであり、松下電器の責任を果たすことになる。
なるほどきみたちが言うように、それは非常に不利な条件ばかりだけれど、若干の経済性を犠牲にしても、この際松下電器は地域の要請にこたえるべきや。そう考えたんで、わしはやることに決めたんや。しかし、これを担当する人は苦労するな。太っている人なら、たぶんちょっとやせるやろな」
しばらくして、この中堅幹部に、"新設の九州松下電器の実務担当責任者として赴任せよ"との命が下った。