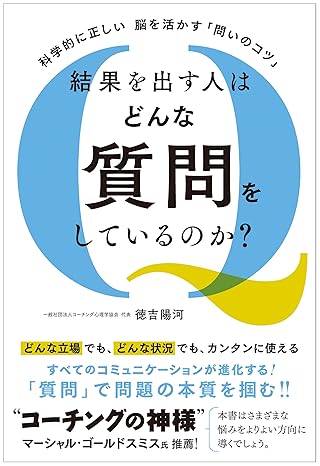相手との信頼関係を築くには「質問」をすることが重要です。人の心を動かすには、会話をする際にどのようなポイントに気を付ければ良いのでしょうか? 本稿では、書籍『結果を出す人はどんな質問をしているのか?』より"相手が心地良いと感じる質問"について解説します。
※本稿は、徳吉陽河著『結果を出す人はどんな質問をしているのか?』(総合法令出版)の一部を再編集したものです
誰かの不幸を喜ぶのは、人間の本質
人の心を動かすためには、ある出来事について「ポジティブな面とネガティブな面」や「したいこと、したくないこと」などを2つ合わせて質問していくのは非常に有効といえます。
これは「ダブル・クエスチョン」といって、こちらが、「相手に関心がある」、「興味をもっている」という姿勢がしっかりと伝わる質問なのです。
対人関係で注意したいのが「シャーデンフロイデ」です。シャーデンフロイデとは、「人の不幸を喜ぶ気持ち」を意味します。
些細なきっかけから、つい誰かの悪口で盛り上がってしまうことは誰でも経験したことがあると思います。これは、人の性格というよりは人の本質といえます。この本質のせいで、共通の知人の悪口などを聞くと、つい巻き込まれて一緒に言ってしまう可能性が高くなるのです。
しかし、ネガティブな気持ちを相手と共有体験すると、誰かを傷つける結果になりかねません。仲間意識は生まれるかもしれませんが、自分も相手もあとで「悪口を言ってしまった」と傷ついてしまいます。
「人を呪わば穴二つ」ということわざがあります。「他人に害を与えれば、自分も害を受ける」という意味ですが、本当にその通りで、悪口を言うと、あとで自分に必ず罪悪感や後悔が芽生えるものです。
ですので、もし悪口が出たときは、次のような言葉で話題を変えましょう。
「ちょっとその話は置いておいて」
「その話題はやめておこうか」
このように話題を逸らして、会話の焦点を変えましょう。
愚痴は徹底的に聞く
ネガティブな面について質問すると、愚痴ばかりになってしまう人もいるかもしれません。
そんなときは、「愚痴ワーク」がおすすめです。
愚痴ワークとは、3分間程度の短い時間で徹底的に相手の愚痴などネガティブなことを話してもらいます。つまり、相手が抱えているストレス、ネガティブ感情を吐き出してもらうワークです。
確かに、愚痴はあまりいいものとはいえませんが、抱え込みすぎるのはそれはそれでよくありません。「この人なりに何かしたい、変えたいと思っているんだな」と前向きに相手の愚痴を受け止めて、相手の悩みや問題を前向きに転換できるように、質問していきましょう。
「今その状況を変えるためにできることは何かな?」
「嫌な相手かもしれないけれど、相手の行動で、何か一つでも見習うべきことはある?」
などといった質問で、ネガティブなエネルギーを人への攻撃ではなく、成長へとつなげられるように促します。
「人の不幸を喜ぶ気持ち」が人の本質にはあるので難しいのですが、その本質も理解しながら、相手が不満に思っている欲求を他のことで満たせるように質問で導くことが大切です。
もし可能であれば、相手の願いを叶えられるようにしましょう。
「感じのいい人」は質問の達人である
ここで突然ですが、身近にいる「感じのいい人」を思い浮かべてみてください。その感じのいい人は、あまり自分語りをしていないのではないですか? きっと、自分から前のめりになって話すのではなく、相手の話に前のめりになって質問をしているのではないでしょうか。
そう、「感じのいい人」はだいたい質問の達人なのです。
そして、こういった「感じがいい」と思われる人に共通しているのは、「傾聴」の姿勢があることです。傾聴の基本は、うなずき、相手に関心を寄せ、注意をもって話を聞くことにあります。
次に会話のペースも重要です。相手が安心できるよう、ゆっくりと話す。または、相手と同じペースで話すことを意識します。
さらに声のトーンも、優しく温かい声色を心がけます。加えて、表情です。なるべく笑顔でいることを心がけてください。話の配分についても、質問をする際は、相手の話を促していく意識をもつとうまくいきます。
「聞き役に徹する」とあらかじめ役割を意識して、決めておくのもいいでしょう。
簡単なコツばかりなので、ぜひ試してみてください。
人は無意識に自分の話をしてしまう
先ほど、「聞き役に徹すると決めておく」と伝えしましたが、なぜ決めないといけないのか。
それは、「人は自分の話をしたい」というのが人間の本質だからです。
人間には「自己中心性バイアス」があり、無意識に会話を自分の土俵にもっていこうとしてしまう性質があります。自分が主体でありたいと思っているため、会話で相手の土俵に連れて行かれたり、相手の話に流されたりするのを本能的に「怖い」と感じます。
これをスポーツでたとえると、敵陣で戦っているようなものといえます。そのため、つい、自分の陣地に会話をもってこようとしてしまうのです。
「そういえば」
「今思い出したんだけど」
「その話はちょっと置いといて」
このような言葉で相手の話を遮ったり、腰を折ったりした経験があると思います。
これを逆の視点から考えてみます。
「え、今私が話してたんだけど......」
「人の話を遮ってまで言うことじゃないでしょう......」
などと思ってしまうのではないでしょうか。自分の土俵で話したいのは、当然ながら相手も同じはずです。
だから、質問に限らず会話をする際は、相手の土俵に乗って会話を盛り上げようという意識をもつと、よりコミュニケーションを楽しんでいくことができます。
これは人間関係において、非常に大切なポイントです。ぜひ、自分中心ではなく、あえて「相手が気持ちよく会話をできる土俵で質問する」ことを、心がけましょう。
とはいえ、完璧主義になる必要はありません。
いつの間にか自分の土俵にもっていってしまったり、ちょっと相手とぶつかってしまったりしても大丈夫です。
そうなった場合に「自分は会話が苦手」と思って落ち込むのではなく、相手の会話を楽しむ、そのコミュニケーションの場をなるべくいい時間、意義のある時間にしていこうと思うことが大切といえます。