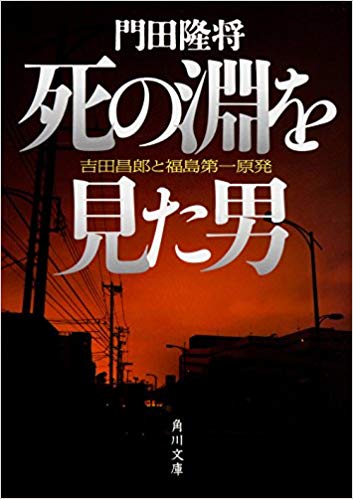「吉田昌郎所長と福島原発“現場”の真実」『死の淵を見た男』が描く当事者の想い
2014年09月12日 公開 2024年12月16日 更新
「死に装束に見えた」
必要最小限の人間を除いて退避――その吉田の指令で免震重要棟は、一種の混乱状態に陥った。言うまでもなく「必要最小限の人間」とは、基準のないものである。どこまでが必要で、どこから必要がないのか、曖昧なのだ。
慌ただしくなった免震棟では、その基準は多くの場合、「自分自身」の判断に委ねられた。伊沢は「技術を持った人間以外は退避して欲しい」と思っていた。年齢が若い人間も同じだ。目の前にいる若い人間に、伊沢は声をかけた。
「おまえ、なにしてるんだ。早く出ろ」
「いや、僕は残ります」
「なに言ってるんだ。おまえは若い。出ろ!」
「いやです」
「これは命令だ。早く出ろ」
そんな会話を交わしながら、伊沢は次々と発電班の人間を送り出していった。
「ありがとうございました」
「お世話になりました」
若い人間が伊沢に挨拶して出ていった。目に涙を浮かべて部屋を出ていった者もいる。しかし、出ていくのは、若い人間だけではなかった。当然残るだろうと思っていたベテランの中にも荷物を持って出ていく者もいた。
生と死の瀬戸際は、どんな時でも残酷だ。覚悟を決めてベントの再チャレンジに行った吉田一弘は、この時、まだ伊沢と共に緊対室にいた。誰が残って、誰が残らないかは、なるべく見ないようにしていました、と吉田一弘は語る。
「あの時、みんなが出ていく時は、ワーッとすごい混乱になりました。沢山の人が退去して、いなくなるわけですからね。僕は、若い人たちに“出なさい”と言っていたほうです。若い人でも“俺は残ります”と言った人もいました。彼らは責任感でそう言ったんでしょうけど、心の中では、もう行きたいと思っていたと思うんですよ。やはりまだ若いですからね。こっちが、“出なさい”というと、若い人は出ていきました」
生と死が分かれる時のその場面は、吉田一弘(当時5、6号機担当の当直副長)は今も思い出したくないという。
「誰が残ったとか、誰がいなくなったとか、できるだけ考えないようにしたのは、それが尾を引くのがいやだったからです。今までつき合ってきて、“おまえは技術者だ”って、信頼できると思っていた人間も、バラバラといなくなるので、できるだけそういうことは考えないようにしました。
年を取った人も、結構、避難していきましたよ。技術を持ってる人間は残らなきゃいけないと、僕は個人的には思っていました。でも、やっぱりほとんどが2F(福島第2原発)の方に避難してしまうと、人間って心細くなるもんですね……」
吉田一弘は、そうしみじみと振り返った。それは、人として極限ともいうべき修羅場だったかもしれない。人間にはそれぞれの家庭や人生がある。同じ職場に同じようにいても、背負っているものがそれぞれの事情によって違うのである。
多くの人間がさまざまな事情によって、2Fへの退避を自分自身で決断したのは「人として」当然のことだっただろう。この時、人の流れとは逆に2階の緊対室に駆け上がったのが、防災安全グループにいた佐藤眞理である。
防災安全グループとは文字通り、こういう災害の時に職員の安全や誘導など、さまざまな作業をおこなうためにいる。地震発生の時、まだ揺れがつづいている最中に、緊急放送設備に飛びつき、所内中に響き渡るマイクで「緊急避難!」と叫んだのも、彼女だった。
しかし、天井の化粧板がバリバリと落ちる中で、緊急放送の回線がちぎれ飛び、彼女の放送はそのひと言で終わっている。以来、彼女は、免震重要棟に踏みとどまって、作業員の世話や食事関係から、現場の消防車の燃料補給に至るまで多くの活動をおこなった。免震重要棟にはこの時、佐藤のような女性がまだ大勢残っていたのである。
「みんなそれまでに、悲惨な状況になっていました。誰もお風呂にも入れないし、そもそも水さえなくなっているんですから。しかも、天井とかも落ちて、みんな頭が真っ白になったまま、そのままいるわけでしょう。
男の人はひげ面で、顔も洗えないんだから、女の人は頭はペッチャンコだし、お化粧っ気もなく、みんな素顔なんですよ。たまたま白いマスクが手に入ると、ちょうど顔を隠せていいな、ってつけてました。
トイレも流れませんからすごいことになっているし、そんな中で、雑魚寝しているわけですから、それはひどい状況でした」
そして、3月15日の朝に、吉田所長による「退避命令」が出たのである。佐藤は、吉田の命令が出た時に1階にいたため、その声を直接聞いていない。だが、続々と退避する人間が1階に降りてきて、事情を知った。
1階には、外に出るための装備がある。タイベックに全面マスク、そして靴にはビニールのカバーをつけて順番に並ぶのである。だが退避する人たちが全員マスクをつけていくと、残って作業をする人間のマスクがなくなってしまう。そうなれば、「現場に近づくこと」ができなくなる。
残る人間のために一部のマスクは隠された。絶対数が足りなくなったため、多くの人の奪い合いとなった。マスクを確保できない人間は、ハンカチを口にあててバスに飛び乗ったり、駐車場に置いてある通勤用の自家用車に分乗していった。
そんな光景を見ながら、佐藤は、ふと自分と一緒に活動していた若い人間が緊対室にまだ残っているのではないか、と思った。もし残っていたら、彼らを死なせるわけにはいかない。佐藤は、そう思って緊対室に駆け上がったのだ。入っていくとシーンとした中で、吉田たち幹部が円卓に座っていた。