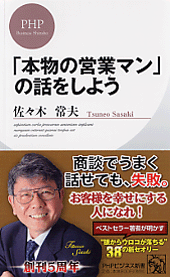言葉の怖さと人間関係の難しさを物語った「失言」
言葉の恐さ。それは一度口に出したものは取り消せない点にもあります。「綸言汗のごとし」とか「吐いたツバは呑めぬ」などというように、いったん口にした言葉は形式的に打ち消すことはできても、完全になかったことにはできません。そのことの恐さは失言の経験のある人ならよく理解できるはずです。
私の現役時代、その失言で出世を棒に振った人物がいました。たいへん優秀な人で、企業のM&Aの交渉などをやらせたら右に出る人はいないというくらい仕事のできる人物でした。その彼があるとき、上司から上層部に提出する予定になっていたレポートの催促を受けたのです。
「この間、頼んでおいた例の報告書だが、あれ、まだかな?」
そのとき忙しく仕事をしていたせいもあったのでしょう、彼はその上司からの問いかけに、なにげない感じで、こんな言葉を返してしまったのです。
「あれですか? あんなもの、いいじゃないですか。たいして重要じゃありませんよ」
その彼の言葉どおり、そのレポートはそれほど大きな重要度をもつものではありませんでした。どちらかといえば、出しても出さなくても、とくに変わりはない程度のものでした。しかしそうではあっても、上司の依頼を「たいしたことない」と否定するのは組織人としてはかなり問題です。
私は横で上司の顔色が変わるのを見て、これはただじゃすまないなと直感しました。やがて、その上司は人事部長に異動になり、社員の昇格の査定を仕切る立場になりました。そうしてその権限によって、くだんの人物の昇格申請をことごとく握りつぶし続けたのです。
上層部の人間がやってきて、「きみ、もう認めてやりなさい。彼の貢献度はけっして小さくないんだから」と失言の主の昇格を促しても、その部長は首をたてに振りませんでした。そのせいで彼は、確実といわれていた役員にとうとうなれなかったのです。
もし、あの失言なかりせば――いうべきでないことをうっかり口にしてしまった彼の過失もさることながら、その言葉を根にもって、他人の人生にマイナスの影響力を行使した上司の行為も責められてしかるべきものでしょう。
組織における人間関係のむずかしさはこんなところにもありますが、同時に、言葉というものはいつもこうしたリスクを含んだ恐ろしい側面も備えている。その事実もよく肝に銘じておくべきです。
言葉はいつも大切に、慎重に扱って、うかつ、おろそかには口を開かないこと。不要な言葉は呑み込んで、必要な言葉だけを吐き出すのが教養ある人間の言葉づかいというものかもしれません。
空の容器ほど大きな音を立てるものです。「もっともたくさん知っている人が、もっとも少なくしゃべる」ともいいますから、やたらと多弁な人は自分の中身が薄いことをみずから吹聴しているようなものかもしれません。
かくいう私自身、自分の言葉の過剰や不足にいつも悩んでいます。余計なことまでしゃべったり、いうべきことをうまくいえなかったり、肝心なことをあいまいにしたり、自分を少し大きく見せようとしたり。言葉づかいの下手なこと、ともすれば言葉を軽く口にしがちなことをしょっちゅう恥じたり、反省したりしているのです。
「善者は弁ならず、弁者は善ならず」とは老子の言葉です。よく自戒したいものです。
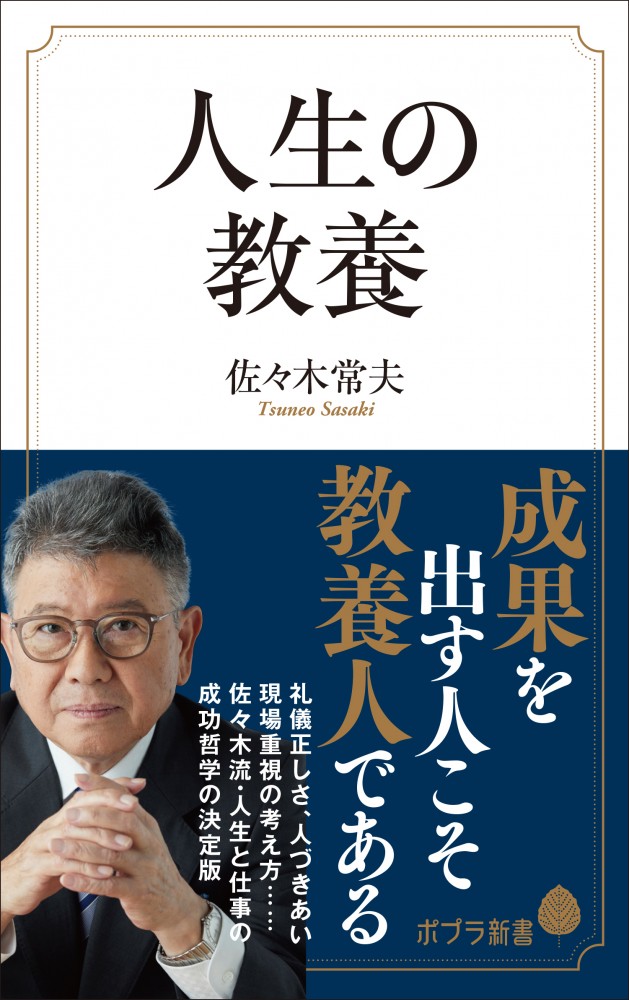
![[図解]人を動かすリーダーに大切な40の習慣](/userfiles/images/book/book_zangyou.jpg)