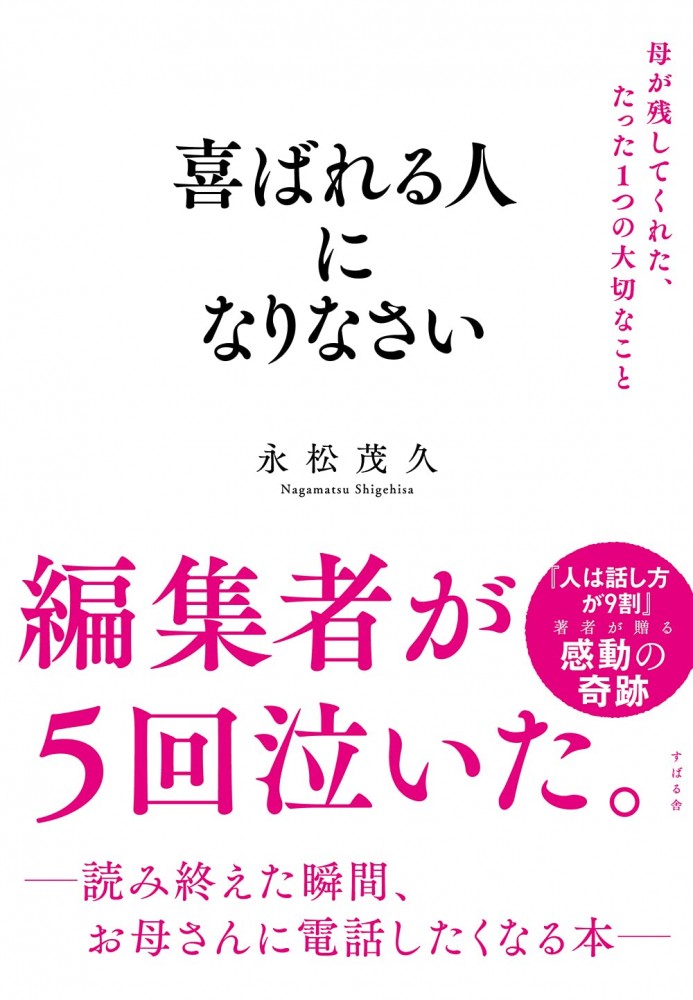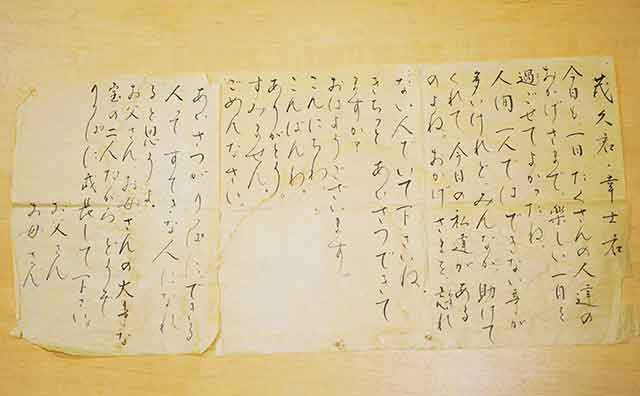ベランダたこ焼き研究所
「母さん。悪いんだけど、家のキッチン貸してくれないかな。あと焼けるとこ」
「わかった。実験にうってつけの場所があるよ」
母は自宅のベランダを提供してくれた。
「たこ焼きの煙で大変なことになるから」という理由で、家の中でやるなということだった。
ただ、雨風だけはしのげるようにと、さりげなく父が屋根をつけてくれていた。
こうして簡易たこ焼き研究所が完成。そこに特注の焼き台を運び入れ、たこ焼き作りがはじまった。
研究の結果、僕のオリジナルメニュー"ヘルシーたこ焼き"が完成した。添加物は一切使わない。とにかくヘルシーさがウリの自慢の新メニューだった。
「試食会をやろう」
「銀だこで勉強してきたたこ焼きはつくらないの?」
たこ焼き研究所でたこ焼きを焼いている僕の横に、母がやってきて言った。
つくろうと思ったらある程度似たものがつくれるのはわかっている。レシピを知っているんだから。しかし、僕は自分の力で生み出したたこ焼きで勝負したい。だから絶対につくりたくなかった。
何を思ったのか、母は「それじゃ、試食会をやろう」と提案してきた。1つは僕の自慢の"ヘルシーたこ焼き"、もう1つは修業してきたものを即興で真似た"銀だこ風たこ焼き"。試食会の参加者はぴったり10人だった。
「どっちがうまい?」
固唾を呑んでみんなの顔を見ていた。
僕にはひそかな自信があった。"ヘルシーたこ焼き"が勝つ。そう思っていたのだ。時代はヘルシー志向に向かっているのだから勝つに違いない。そう信じていたのだ。
みんなが食べ終わり、結果発表。
6対4で惜しくも負け、なんて、それくらいならまだ格好もつくのだが、なんと実際は10対0。
"ヘルシーたこ焼き"は完敗した。コールド負け。
何も言わずにみんなが食べるのを見ていると、"銀だこ風たこ焼き"のほうはかたっぱしからなくなっていく。
「これうまいな。茂久、よくがんばってつくったな!」
というほめ言葉が聞こえてくる。一方の自信作"ヘルシーたこ焼き"はというと、「こっちは普通だな」と言われいつまでも皿の上に残っていた。
みんなから、"銀だこ風たこ焼き"を前に「このたこ焼きならいけるぞ!」と言われた。喜んで食べてくれるみんなの顔を前に、まったく笑えない僕がいた。
我を抜きましょう
その後の父との会話で、僕の商人そして著者人生の中で忘れることができない、大きな気づきをもらうことになる。
試食会の大敗の後もせっせとたこ焼きを改良し続ける僕に、ある日父がこう聞いてきた。
「お前どうするつもりだ」
「負けちゃったけど俺は"ヘルシーたこ焼き"でいくよ。自分のたこ焼きで勝負したいから」
「そうか。じゃ、お前、もう仲間に声かけるのやめたほうがいいぞ」
その頃すでに、オープンしたらたこ焼き屋を手伝ってくれるという仲間がいた。
「あいつらとじゃなくて、お前1人でやれ。それなら俺は安心だ」
「なんで?」
「お前は自分が喜びたいだけだろ。みんなあのたこ焼きを喜んで食べてくれている。お前が修業してきたたこ焼きをな。あれは俺も売れると思うよ。でも、それを商品にしないっていうのは、お客さまの求めるものよりも、自分のこだわりを押しつけて、お前が喜びたいってことだよ。お前がやりたいなら勝手にやればいい。でも、それなら人を巻き込むな。それなら文句は言わないよ」
「あなた、もうちょっと優しく言えばいいのに」
そうだ。モノには言い方ってもんがあるだろ。母さんが言うようにもっと優しく言ってくれればいいのに。
ふてくされる僕に対し、さらに親父は追い討ちをかけるように言った。
「商人をなめるんじゃない! 商人てのは売っただけじゃなく、働いてくれた人たちに給料も払っていかなきゃいけないんだぞ。本当にお前が商人なら、10対0で勝ったほうのたこ焼きでいくはずだ。まずは自分が儲けて、自分の生活ができるようにして、そこからスタッフだろ。でも、もう手伝ってもらうことが決まっているなら利益を出すしかない。それをもう1回考え直してみたほうがいいぞ。"我"ってのは商人の大敵なんだぞ」
ぐうの音も出なかった。商人の先輩として言ってくれた父の言葉に反論できるところなんて、まったくなかったからだ。