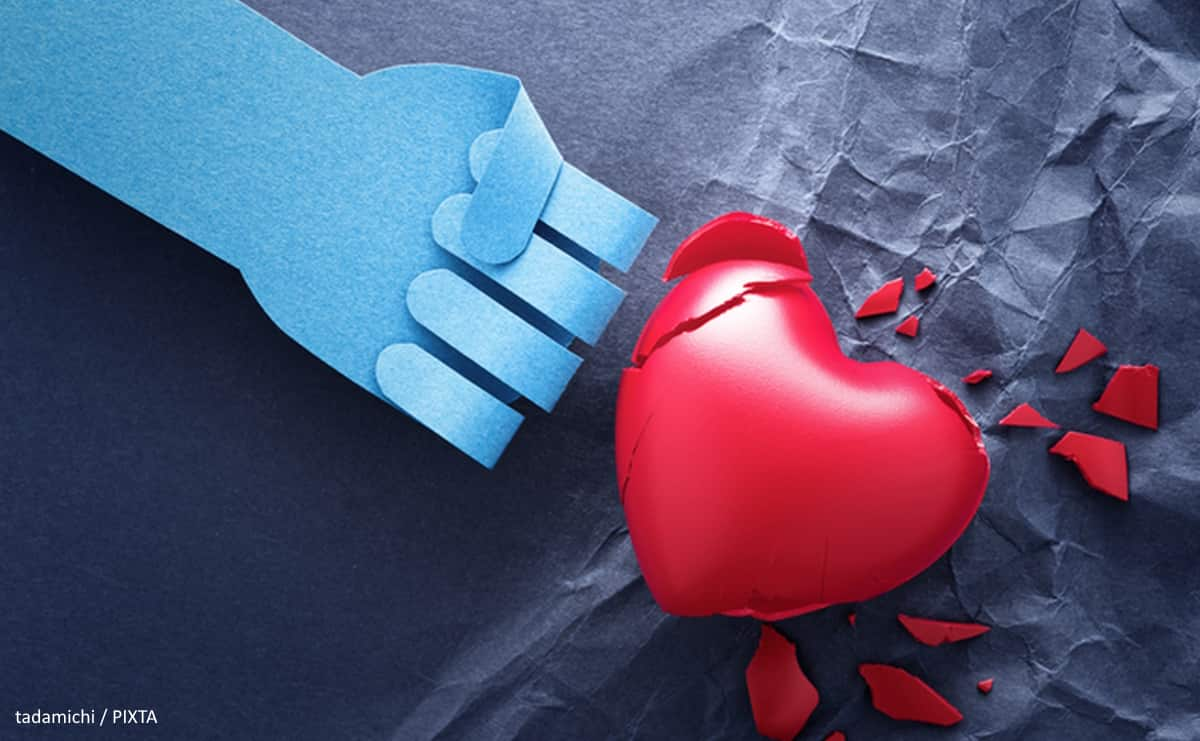修道女であり、ノートルダム清心女子大学で初めての日本人学長となった渡辺和子さん。生前は病に倒れながらも、最期まで沢山の人々に寄り添い、お仕事に尽くされました。
渡辺シスターの遺品から見つかった原稿を編んだ一冊『あなたはそのままで愛されている』より、"許し"について語られた一節を紹介します。
※本稿は、渡辺和子著『あなたはそのままで愛されている』(PHP文庫)より、内容を一部抜粋・編集したものです。
私が許された日
許すということは、私にとって、たいそう難しいことでした。自分の友達の裏切り、日常生活の中のずるさ、同僚のミス等には我慢がならないことがありました。
そんな私が、大学卒業後、今の上智大学国際学部で働いていた時のことです。宣教師でもあった上司の外国人は、私に、仕事の合間を縫って、大学院に通うことを許してくれ、あまつさえ、卒論に苦しんでいる時には、親切に英語を直してくれたのでした。
その日も、親切に英語の間違いを直し、内容の貧弱さを指摘してくれたというのに、私はといえば、多くの修正を余儀なくされてプライドはズタズタにひきさかれ、感謝するどころか、不機嫌になり、今思い出しても顔があかくなるような態度をとっていたのです。
昼時になって、宣教師は昼食に修道院へと戻り、私は、すごくみじめな思いを抱いて、砂をかむような思いで自分の昼食を終えました。
(無償で、自分の時間をさいて教えてくださったのに、私の態度は何だったろう......)
もう教えないと言われても、私には弁解のしようもないのです。
ところが、昼食を終えて、再び戻って来た宣教師の顔は晴れやかで、
「続きをしましょう」
とにこやかに言ってくれました。
私は、その時に「許し」の本来の姿にふれたように思います。
許しを乞わねばならないのは私なのに、それに一言もふれず、親切を続けてくれる人に出会い、恩知らずと突きはなされてもかまわないのに、温かく受け入れられた、あの日の感激が今も私には鮮やかに残っていて、「許し」とはこういうものだと教えてくれているのです。
「許し」の本来の姿は
人の過ちを受け入れ、
変わらず接すること。
――許しを乞わねばならない相手から許された感激の中で、許すことの意味を知った。
不完全さとの出会い
「許し」とは居丈高に相手に与えるものでも、「かわいそうに」と憐れんで賦与するものでもなく、「歩み寄ること」です。
ちょうど、聖書の中で、放蕩息子が戻って来るのを見て、父親が、走り寄っていったように。そして"優等生"だった兄が、やきもちをやき怒るほどに、無条件に許し、馳走をしてやる愚かさなのです。
人間というものは、許された経験があって、はじめて他人を許すことができるようになるものです。ちょうど、愛されて、愛することができるようになるように。
私には数多くの出会いがありました。それが「私らしさ」を作ってくれたのです。しかし、それは出会いが、自動的に私を直したのでも変えたのでもなく、その出会いをやはり、自分が受けとめたことによるのだと思います。
ということは、今までに、もしかしたら、もっともっと多くの「出会い」があったのだろうに、逃がしていたということでもあるでしょう。
でも、それでいいのです。人間は所詮、何もかも完璧である筈がないのですから。
だからこそ、人にも完璧を求めるべきではなくて、他人の不完全さを通してさえも「自分らしさ」というものが形成されてゆくのでしょう。
「許し」とは
相手に与えるものではなく
愛をもって歩み寄ること。
――不完全であるにもかかわらず無条件に許されたことのある人は、その経験から、他人を許すことができるようになる。
平常心を保って生きる
「シスターの心にも波風が立つ日がおありですか。いつも笑顔ですけれども」一人の大学生の質問に、私は答えました。
「ありますよ。他人の言葉や態度に傷ついたり、難しい問題にぶつかって悩んだりする時に、平常心を失うことがあります。ただ、自分の動揺で、他人の生活まで暗くしてはいけないと、自分に言いきかせ、心の内部で処理する努力をしているだけなのですよ」
私は、母から受けた教育をありがたいと思っています。小さなことでクヨクヨしていた私に、母は申しました。
「人間の大きさは、その人の心を乱す事柄の大きさなのだよ」
この言葉が、折あるごとによみがえり、私に事柄の大きさを考え、つまらないことに自分の時間とエネルギーを費やしてはもったいないと思う習慣をつけてくれました。平常心に立ち戻ることを可能にする一つの秘訣です。
母は結婚のため、愛知県の小さな町から東京へ出て来ての生活の中で、父の地位にふさわしい教養を身につけるまでには、辛いことも多かったようです。その母が、自分の経験から子どもたちに伝えた言葉には、説得力がありました。
「人は皆、自分が一番かわいいのだから、甘えてはいけない」
期待しすぎるから、期待はずれの時に腹が立ち、平常心を失うのです。
期待してはいけないというのではありません。ただ、自分も他人も、弱い人間であることを心に留めて、「許す心」を忘れないでいるようにという戒いましめでした。
醒めた目で問題の大きさを見極め、温かい心で人間の弱さを包むこと。このような「目と心」のバランスが、平常心に立ち戻り、それを保ちながら生きる私の毎日を、助けてくれています。
醒めた目と
温かい心があれば
平常心でいられる。
――自分も他人も弱い人間だからこそ、「許す心」を忘れないようにしよう。