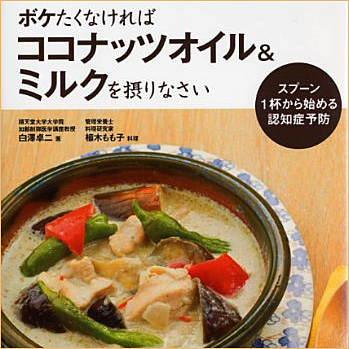[薬毒同源]食べ物は毒にも薬にもなる
2015年04月02日 公開 2024年12月16日 更新
《PHP新書『毒があるのになぜ食べられるのか』より》

食べ物は毒にも薬にもなることは、先にも述べたとおりです。食べ物が毒となったり、薬になったりする、そのことの意味を改めて考えてみましょう。
著者は「薬毒同源」を提唱しています。すなわち、薬は「諸刃の剣」であることを意識に入れておかないと、薬として摂取しているつもりが毒というしっぺ返しを食うことがあるということです。日常的に摂取する食べ物にも同じことが言えます。間違った食べ物の組み合わせ、間違った摂取方法もありえます。「食べ物のなかの毒」は、表面的には見えなくとも、常に身近なところで浮き沈みしている現象であることを心の片隅に留めておく必要があるのではないでしょうか。薬に副作用があるように、食べ物にも毒となる可能性があります。このような食べ物たちとうまく付き合うことを考えましょう。
食べ物があれば毒と薬がある
食べ物は、もともと「毒や薬」と深い関係があります。私たちの祖先は、自然界の動植物のなかで食べられるものを探索する過程で、毒のあるものや薬となるものを見いだしてきました。いずれもはじめは「まずは口に入れてみる」という体験があり、その後の経過を客観的に観察するという共通の経験かあったのでしょう。それを何回か試行錯誤することで、毒や薬を見いだすという状況が展開してきたのだと思います。その基礎となる知識を振り返ります。
薬食同源と医食同源と薬毒同源
「薬食同源」という考え方は古く中国から伝わりました。薬と食べ物とは源が同じであるという思想です。食べ物と薬との関係というものは、私たちが普段考える以上に深いと思われます。
食べ物のなかには私たちの体調に影響を与えるものが多くあります。大根おろしを食べると消化にいいとか、ヤツメウナギは目にいいとか、健康のために黄緑色野菜を食べましょうとか、ショウガは体を温めるとか、元気を付けるためにはニンニクを食べましょうとか……。このようなたぐいの言葉はたくさん耳にすることでしょう。結局これらは食べ物が薬の役割もしているためと考えて間違いありません。天然に存在する薬効をもつ産物を長い間私たち人間は利用してきたのです。
かつて、わが国には旧暦の5月5日に「薬狩り」という風習がありました。611年55月5日、推古天皇は大和の兎田野に、鹿の若い角と薬草の採集に訪れています。その後、薬狩りは恒例行事になったと『日本書紀』には記されています。鹿の角を「鹿茸〈ろくじょう〉」といい、不老長寿の3大妙薬のひとつとされました。薬草のなかには菖蒲やヨモギなどの香りの強いものもあって、後に今日に続く、菖蒲湯に入ったり、粽〈ちまき〉を食べたりする風習につながります。また、「薬玉」といって、香りの強い沈香や丁子を錦の袋に詰めて玉とし、菖蒲やヨモギを添えて五色の糸で玄関に吊るすことも行われました。
ちなみに、陰陽思想では、奇数は陽で、1、3、5、7、9を組み合わせた月日は薬と関わっていて、1月1日は「お屠蘇」(一年の邪気を払う意味で、酒やみりんで様々な生薬を浸け込んだ薬草酒を飲む)、1月7日の七種粥、3月3日は「桃の節句」(桃の種子から調製される「桃仁」は女性の疾患などに効果がある)、9月9日の重陽の菊の節句には5月5日にかかげた薬玉を、菊花を絹に包んだものに取り替える風習があったのです。重陽とは陽数の極みである9が重なるという意味で、平安時代には邪気を払う菊を飾ったり、菊の花を浸した菊酒を飲み長寿を祝いました。清少納言の『枕草子』にも「九月九日の菊を綾と生絹〈すずし〉のきぬに包みてまゐらせたる、同じ柱に結ひつけて月ごろある、薬玉に取りかへて捨つめる。また薬玉は菊のをりまであるべきにやあらむ」(四六段中葉)とあります。
なお、冬に保温・保健のために鹿や猪の肉を食べることを、「薬食い」と呼びました。
一方、私たちの祖先は種々の食べ物を欠くことによって病気になることを知りました。新鮮な野菜や果物を欠くことにより壊血病になることを知り、玄米食から白米食となることによって脚気を引き起こすことや、さらにはトウモロコシを主食とすることによってペラグラを引き起こすことも知りました。これらは、現在、それぞれ、ビタミンC、ビタミンB1、そしてトリプトファンの欠乏症であると解明されています。よって、これらの欠乏症(病気)に対しては、ビタミンC、ビタミンB1、そしてトリプトファンを含む食事は薬となるわけです。
先に述べたように、薬食同源は中国から日本へ伝わった言葉でしたが、なぜか「薬」という字が化学薬品を思い起こして誤解されやすいとして、わが国では薬食同源のかわりに「医食同源」という言葉が考えだされました。これは1972年のことで、NHKテキスト「きょうの料理」9月号に発表されました。発案者は、東京都で医院を開業していた新居裕久氏(1928~2008)。新居氏は「食べ物は飢えたときとれば食であり、病のときとれば薬である」とも言っています。
一方、私は「薬食同源」に対して2005年ごろより「薬毒同源」を唱えています。生体に作用を及ぼす生物活性物質は、量によってまた使い方によって毒にも薬にもなりうるということです。たとえば、ストリキニーネは強い毒ですが、ストリキニーネを含む生薬である馬銭子〈まちんし〉を少量含む製剤は、インドでは健胃薬として使われています。ボツリヌスの毒であるボツリヌストキシンは世界最強の毒のひとつですが、現在、美容や斜視に応用されています。薬と毒とを厳密に区別することはできず、薬にもなり毒にもなるという視線で見ることが重要であることを肝に銘ずるべきです。
薬膳料理と七種粥
薬膳料理にはそのメニューに気を配るだけでなく、そのレシピや調理法にもぜひ注目していただきたいと思います。各食材の食べ方にはそれなりの理由のあることも多いのです。
たとえば灰汁抜きです。灰汁抜きには食べる際の食味を向上させるために、えぐみ成分を除く意味合いがあります。しかし、えぐみ成分のなかにはシュウ酸のような毒作用を有するものもあり、このような化合物をしっかりと除く意味もあるのです。
また、食べ物のなかには種々の薬理作用の知られているものが多くあります。たとえば、赤小豆には利尿作用があります。冬瓜は体の熱をさまし、必要な水分を補ってくれます。一方、カボチャやネギには体を温める作用があり、ともに風邪の予防にもなるといわれます。
薬膳料理としては、直接的にはっきりした薬理活性を望むことよりも、このような穏やかな、しかも何らかの良い作用のあるものを私たちの生活のなかに取り入れていくという姿勢が大切ではないかと思います。
薬膳料理といっていいものかどうかはお任せしますが、わが国には「七種粥〈ななくさがゆ〉」という行事があり、五節句の1つとして正月7日に春の7種の植物を入れて粥を作って食べる習慣があります。何ともいえぬ「春の息吹」の感じられる行事です。
春の七種は、四辻左大臣(四辻善成/1326~1402)により、「セリ ナズナ ゴギョウ ハコベラ ホトケノザ スズナ スズシロ これぞ七草」と詠まれています。しかしながら、もともとはとくに決まりはなく、何でもかんでも入れていたらしく、たとえば、この季節、雪の深い秋田では前記の七種は手に入りにくいので、「セリ、ゴボウ、ダイコン、タラの芽、キノコ、油揚げ、ネギ」などを用いるとのことです。また、後世には単にナズナまたはアブラナのみを用いる場合もあったとのことです。現在では、おせち料理で疲れた胃をいたわるという意味があり、また、野に芽吹く若草の生命力にあやかり、不足がちの野菜を補うというような意味があるのでしょう。
一方、「秋の七種」のほうはもっぱら観賞用です。『万葉集』第8巻に山上憶良(660?~733?)が詠んだ秋の七種の歌2首があります。その歌とは、「秋の野に 咲きたる花を指折りてかき数ふれば七種の花」(1537)と「萩の花尾花葛花なでしこの花女郎花また藤袴 朝貌の花」(1538)で、ここでいう朝がほは、現在のキキョウに該当するというのが定説になっています。
<<次ページ>>酒の効用と毒