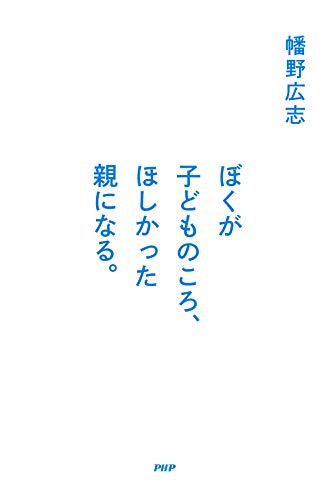価値観を守るために「医者とケンカ」できるか
もちろん、主治医とのウマは合いません。当然1〜2週間入院することが必要な期間でさえ我慢できない夫は、2〜3日で「もう帰る」と言い出します。
こんな夫のことは「言うことをまるできかない面倒な人」と見られていたことでしょう。もしかすると、「奥さんは看護師なのに、なんで夫ひとり説得できないんだ」と思われていたかもしれませんね(笑)。
「治療もせずに家に帰るんだったら、あなたのことはもう診ないよ」
夫は主治医から、何度もこんな言葉をかけられていました。
普通の神経の持ち主であれば「先生のおっしゃる通りにいたします」と従うでしょう。でも、そこは根性のある夫、「診ないよ」と言われると「ありがとうございます」とすかさず返していました。もちろん、主治医はカンカンです。
でも、夫にとっては、それが「ベストアンサー」。他の人の価値観と、どれだけ異なっていても、彼にとってはそれがベスト。
それはそれで、仕方がありません。結局、在宅療養の間にのべ3回も管の交換の処置のために入退院を繰り返しました。
2回目の管の交換のあと、容態が急変して救急車で運ばれ、強制入院になったことがあります。今回ばかりはじっくりと入院加療が必要だと、医者からはされました。
しかし夫は病院から脱走して、体中にチューブを巻き付けたまま、ひとりで電車に乗り、着の身着のまま自宅に"逃げ帰って"きました。
私は、「夫はそこまで病院が嫌なのか」というショックと、驚きと、病院への申し訳なさで、玄関に立ち尽くしました。
一方、息子たちは、父親をひと目見て「あっぱれ!」と褒め、ゲラゲラとずーっと笑い転げていました。そんな明るい息子たちに気勢をそがれた私は、怒る気力もスーッとなくなり、「とりあえず病院へ戻ろう」と説得をする気分も消え失せました。
食べられなくても「芋焼酎」は飲める
病床にある夫と過ごしていると、「看護師の立場としては」という建前が、いくつも崩れていきました。たとえば、お酒を飲みたがる夫にどう対処したものか、最初は悩みました。もともと彼は無類の酒好き。晩酌を欠かさない人だったのです。それも、決まって芋焼酎のストレートでした。
先の長くない人なのだから「少量のお酒であれば"アルコール消毒"になるだろう」「体も温まるだろう」と自分自身に言い聞かせ、用意するようにしました。
主人がおいしそうに目を細めてお酒を飲む姿は、今でも鮮やかに覚えています。
そのうち、酒好きの夫に大きな問題が降りかかりました。おちょこすら持てなくなってきたのです。私が彼の口元に、おちょこを運ぶことが増えました。
こんな私の姿を目の当たりにしていたからでしょうか、息子たちも、食事介助をよく手伝ってくれました。
当時、長男は看護学生、次男は小学2年生でした。
あるときから、私は10種類ほどのおかずを少しずつ用意して、それらをひとつひとつ夫の口元に運び、食べられるものを探すようになっていました。
その「食べられる」「食べられない」というところにゲーム性を見出したのか、息子たちは食事介助をすすんで手伝ってくれました。
「これは食べられたよ!」「無理だったよ」
他人様から見れば、自分の親に対して失礼で、不謹慎な行動だったかもしれません。でも、そんな不真面目な明るさがあったからこそ、私は続けられたのです。
そのうち、息子たちの出番も徐々に減るようになってきました。いよいよ、固形物が食べられなくなり、さらには「流動食」も夫はほしがらなくなってきたのです。それは「おいしくない」ということではなく、もう「食べないでよい」という体のサインだったのでしょう。
救いは、夫がお酒を変わらずほしがってくれたことです。ただ、もうそのころになると、おちょこからは飲めません。そこで私は、シリンジ(注射器のような形の、液体を注入する医療器具)で、夫の口にお酒を「入れる」ことにしました。
一般的な医療関係者の方が知ったら、卒倒する人もいるかもしれません。でも、私は夫が喜んでくれるのを見て「それでよい」と感じていました。