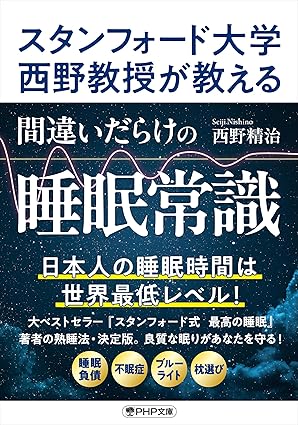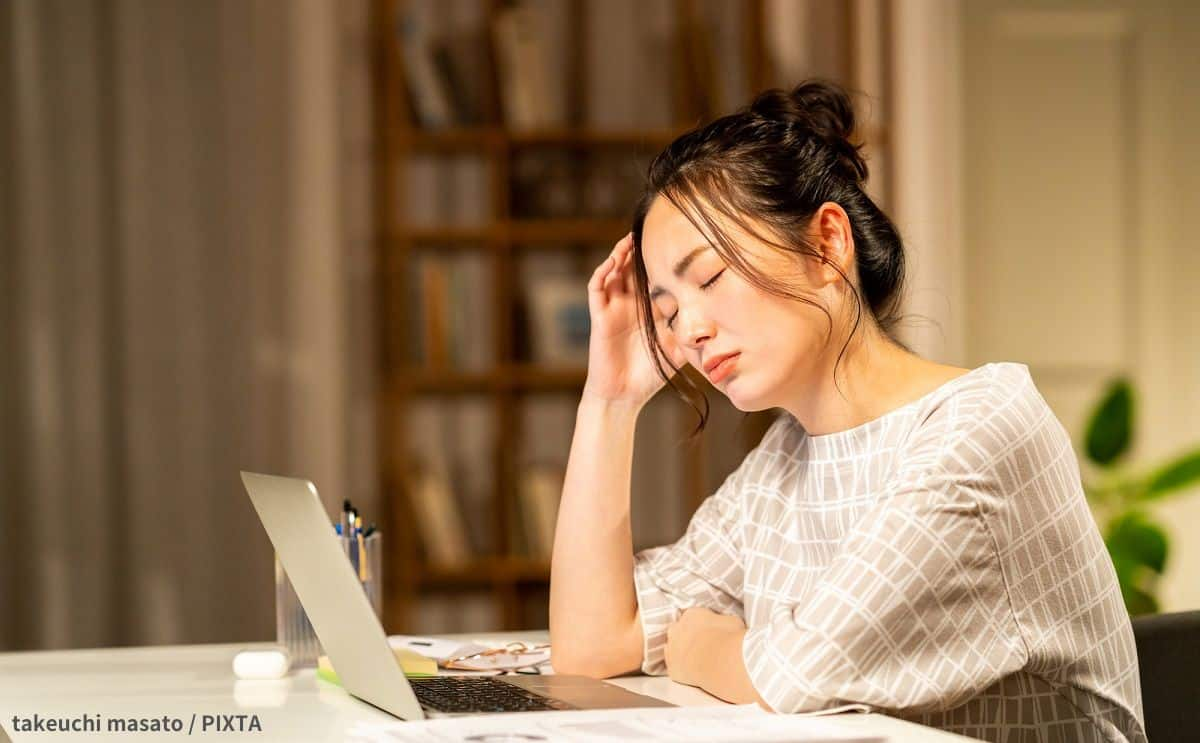体内時計の乱れは、睡眠障害だけでなくホルモンバランスや自律神経にも影響し、食欲不振やうつ症状を引き起こす可能性があります。こうしたリズムの乱れは「概日リズム睡眠障害」と呼ばれています。スタンフォード大学医学部精神科教授・西野精治さんによれば、シフト勤務者の多くが体調不良を抱えているそう。書籍『スタンフォード大学西野教授が教える 間違いだらけの睡眠常識』より解説します。
※本稿は、西野精治著『スタンフォード大学西野教授が教える 間違いだらけの睡眠常識』(PHP研究所)の一部を再編集したものです
シフト勤務者の多くが体調不良を抱えている
日本ではいま、交代勤務で働く人の割合が3割近くになっていると聞いたことがあります。その多くが、睡眠障害、めまい、消化器系等の不調、勤務時間中の眠気、倦怠感などの問題を抱えているといいます。交代勤務に伴うこうした体調不良も、「概日リズム睡眠障害」の一種です。
ただ、交代勤務とひとくちにいってもさまざまな勤務体系があり、産業による特徴もあります。2交代や3交代など夜勤のパターンによっても異なりますが、日本では、月に5〜8回(週に1〜2度)程度の夜勤が一般的です。救急指定病院や入院患者さんのいる病院では、看護部門は日勤・準夜勤・深夜勤の3交代制、医師・薬剤部・検査部門は宿直勤務が多いです。
消防署、あるいは、警察署(交番)、警備業の施設警備部門などでは、いつ発生するかもしれない火事・事故・事件に備え、当番者が深夜も含めた24時間待機の体制をとっています。消防署・警察ではそのため、2部あるいは3部勤務が導入されており、この勤務体系も、2交代、3交代とよばれることもありますが、看護部門等の勤務体系とはまったく異なります。
一方、車の製造業では、昼夜の2交代(連続2交代勤務)を1〜2週間交代で行なっているところもあります。これら2交代制の利点は、深夜勤務手当を節約できること、また連続2交代勤務では需要の変動を残業(最大3時間×2)で吸収できることがあげられますが、これはあくまでも、従業員の健康問題を度外視して表面上の経済性を目的とした交代勤務です。
こういった1〜2週間交代の連続2交代勤務による健康被害や、就業中のパフォーマンスの低下により経済性においてもマイナスの影響を与える可能性が高いので、今後その見直しが迫られると思われます。
これまでのシフトワーク研究のほとんどは、シフトワークが身体に悪影響を及ぼし、生産性に悪いというネガティヴな側面に関する報告にとどまっており、その改善策については手つかずの状態でした。
そこで、私は2022年にシフトワーカーのウェルビーイングの向上を目的としたNOBシフトワーク研究会を立ち上げました。この研究会では、睡眠や生体リズムの専門家だけでなく、時間栄養学、スポーツ医学の専門家、数学者、企業の経営者、勤務管理者に参加していただき、改善策について議論し、推奨していくことを目指して活動しています。
2カ月に一度、誰でも参加できるオンライン講演会も開催し、自由に議論を行う場を設けていますので興味のある方はぜひご参加ください。参加登録は無料です(https://nobshiftwork.com/about/)。
身体本来のリズムにそぐわない時間帯の就業であっても、覚醒度を上げ、パフォーマンスを向上させるにはどうしたらいいか。対策のひとつに、交代勤務の現場でも、「光療法」の活用があります。
たとえば、夜間に稼働している職場で高照度のライト、特にブルーライトを使うと、メラトニンの分泌を抑えることになるので、勤務中に眠くならないのです。イメージとして、野球場のナイター照明を思い浮かべてもらえばいいでしょう。
ナイター照明は、非常に明るく感じます。暗いと、プレイするほうも観客もテンションが上がりません。あの煌々とした明るさには、パフォーマンスを上げる効果があるのです。
夜にブルーライトを浴びることは、身体が本来もっているリズムのためにはいいこととはいえません。
ただ、現代社会で交代勤務をまったくなくすことは不可能です。交代して夜間でも働かなくてはいけないのであれば、眠くなってうっかりミスが起きてしまうよりは、眠くならず、意識が覚醒しやすい環境をつくるべきでしょう。その場合、朝に仕事を終えた後、さらに朝日を浴びてしまうと体内時計は完全に混乱してしまい、眠れなくなります。
ある事業所では、夜間勤務を終えた人たちに、日中は室内を意識的に暗くして過ごしてもらうようにしたところ、睡眠が改善されたという報告もあります。生体リズムには反していますが、体内時計を完全に昼夜逆転させてしまうわけです。
身体には順応性があります。逆転生活でも、きちんとメリハリをつけて新たなリズムを確立することができれば、睡眠もしっかりとれますし、覚醒時の仕事効率が劣化することもありません。
仕事の敵、アフタヌーンディップの撃退法
昼食後の午後2時ごろになると、「どうも、やる気が低下する」「眠気が出てくる」、こんな経験はありませんか?
それは、「アフタヌーンディップ」。
昼食を摂って満腹になることで、脳への血流が減るからといわれますが、むしろ、これは体内リズムの問題です。昼食を摂ろうが摂るまいが、覚醒レベルがちょっと低下しやすい時間帯なのです。
霊長類の猿なども、この時間帯によく昼寝をしますので、私は、「アフタヌーンディップ」は、系統発生による昼寝のなごりではないかと思っています。
とはいえ、昼食を食べすぎると、満腹感から気だるさが出て、意欲が低減しやすいことは確かです。ランチは適度な量にしておいたほうが、午後のパフォーマンスにはいいと思います。
アフタヌーンディップを撃退するには、覚醒系の神経伝達物質が活発になるようにすればいいのです。
たとえば、ものを「嚙む」ことは、脳を活性化させる働きがあります。ランチも、量をたくさん食べるのではなく、よく嚙んで食べることを意識すると、脳にも、消化にもいい。ガムを嚙むというのも眠気覚ましに効果があります。
メジャーリーグの試合を観ていると、選手たちはプレイ中によくガムを嚙んでいます。あれには、意識の覚醒度を高めるのと、よけいな緊張による力みをとる、ダブルの効果があるといわれています。
力んでしまうと肩や腕にへんな力が入ります。口もぐっと食いしばるような感じになる。しかしガムを嚙んで顎を動かしていると、その力みが抜ける。ですから、アメリカのスポーツ選手は、ガムを嚙んでいることが多いのです。
眠気撃退の定番といえば、カフェイン。カフェイン入りの飲み物の代表格がコーヒーで、世界中で古くから愛用されています。紅茶や緑茶にもカフェインは含まれています。
カフェインは、動物の体内では構成できない植物由来の覚醒を促す物質。DNAなどの核酸成分でもあり、眠気を促すアデノシンという物質の作用に対抗します。
冷たい飲み物のほうが目が覚める気がするかもしれませんが、身体の深部体温を高めるほうが活動量を上げられるので、温かい状態で飲んだほうが効果が期待できます。
核酸は微生物も含め、すべての生物の構成成分ですので、睡眠の起源は非常に古いものだと私は考えています。アデノシンを介して睡眠を調節することは、太古から存在し、植物や下等生物から人類まで必要としてきた......などと想像を膨らませてみるのも眠気覚ましによいかもしれません。
強烈な眠気があり、能率が落ちてしまうようなら、やはり仮眠をとるのが正解です。「パワーナップ」をとることをお勧めします。
オフィスに、そのための仮眠コーナーが設けられていると、休憩しやすくなります。ベッドを用意したり、個室にしたりというような大げさなものでなくても、その一角だけ明かりを落とし、リクライニングできるチェアを用意しておいて、アイマスクをかけて寝るくらいの感じで十分でしょう。
なまじベッドなどがあると、つい長く横になってしまいたくなるので、20分程度の仮眠には、首や肩などをリラックスさせられる程度のシートのほうがちょうどいいのです。
こそこそと寝るのではなく、眠気も疲れも吹き飛ばし、リフレッシュして能率アップを図るために、積極的に、正々堂々と20分ほどの仮眠をとる。
睡眠負債を抱えがちなビジネスパーソンの体調管理の一環として、もっと広まってほしい習慣です。
「睡眠時間を削る」前に考えること
「どうして、こうも毎日が忙しくなってしまったのか......」
こんな疑問を感じませんか?
インターネットの普及以降、時間の回り方が急激に変わったように思います。買い物も、自分で店に出かけていかなくても、ネットでポチッとやれば注文できて、届けてもらえる。ものすごく便利になって、時間をかけなくてもよくなっているのに、その分、空き時間ができているかというと、そんなことはありません。
むしろ前よりも忙しい。
それは、以前なら数カ月かけてやりとりしていたことも、スピードアップした対応が求められるようになっているから。
たとえば、専門的な研究論文の査読なども、以前は2カ月くらいかけて読んでレスポンスすればよかったのが、いまは2週間以内くらいに時間が短縮しています。査読に要する手間が何か軽減したわけではないのですが、すばやいレスポンスが求められます。
早くやったら後が楽になるかというとそうではなく、何か動くごとに、処理しなくてはならないことがさらにどんどん増えていきます。
現代は、情報量が圧倒的に増え、それにともない活動量、処理しなければならないことも、加速度的に増えているわけです。みんな、時間が足りない―。ですから、どのように時間を捻出したらいいか、タイムマネジメント、時間術のアイデアが欲しいわけです。
睡眠を論じるうえで、生理学の知識と時間術とでは土俵が違うといいましたが、このような状況のなかで「脱・睡眠負債」を目指すためには、時間術的な視点も必要になります。
一生のうちの3分の1もの時間を費やすことになる睡眠時間をどのように捉えるかという問題にもつながっていきます。
1日24時間という時間は変わらないのです。そのなかで、自分は何の時間に価値を置くのか。それぞれの価値観によって、「何を無駄な時間と考えるか」は違います。
しかし、その無駄を削ぎ落としていくとき、そこに睡眠時間をカウントすべきではないと、私は睡眠研究者として声を大にして言いたいのです。睡眠時間はきっちり死守し、起きている時間のなかで無駄を削っていくべきです。