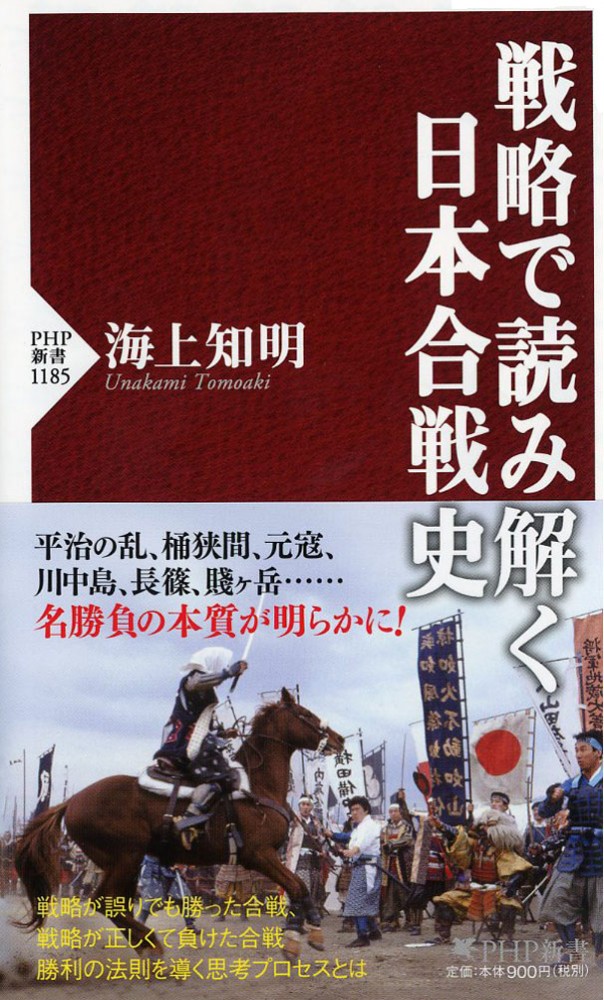「手勢15名からの逆転完勝」 平治の乱で平清盛が見せた“完璧な合戦”
2019年05月09日 公開 2024年12月16日 更新

<<NPO法人孫子経営塾理事である海上知明氏が、近著『戦略で読み解く日本合戦史』は、日本史の一次史料にとどまらず、『孫子』やクラウゼヴィッツの『戦争論』など古今東西の戦略論を参照しつつ、日本合戦史を分析している。
同書にて、海上氏は平清盛を時代の最有力者に押し上げた「平治の乱」の鎮圧を「完璧な合戦」と賞賛している。この合戦を分析した一説を紹介する。>>
※本稿は、海上知明著『戦略で読み解く日本合戦史』(PHP新書)より、一部を抜粋編集したものです。
『孫子』と『戦争論』を複合させた
戦略で古戦史を分析していくとき、最初に取り上げる合戦は、戦略の構造を見るモデルケースとなるものが望ましいように思える。その意味で最もふさわしいのが、平清盛による「平治の乱」の鎮圧である。
上杉謙信と武田信玄による「川中島合戦」が最も華麗な戦略の姿を示すものならば、大政治家にして名将であるという「万能の巨人」平清盛による「平治の乱」の鎮圧は最も完璧な戦い方である。
「平治の乱」の鎮圧の完璧さというものは、あらゆる角度から見ても落ち度がないことに象徴されている。そして『孫子』と『戦争論』を複合させたという意味で特筆される。
今から2500年前に孫子(孫武)が著した『孫子』と、200年前にクラウゼヴィッツが著した『戦争論』は古典的戦略論として東西の横綱である。両書とも普遍的であり深遠な哲学であり、多くの人が一冊だけ戦略論の本を挙げろと言われたら『孫子』か『戦争論』のいずれかを出すだろう、と言われている。
ところがこの東西戦略書の双璧たる両書は、しばしば対立的なものとして取り上げられることがある。
孫子は戦争の要素を抽出しているのに対し、クラウゼヴィッツは戦争の本質は何かを分析している。
孫子が生きた2500年前は分業が未発達の古代に当たり、役割分担も曹操がそうであったように一人の指導者が時には政治家であり、戦略家であり、戦術家であることもあったが、クラウゼヴィッツは近代の人で、分業の発達を受けて戦略と戦術の区分を定義している。
『孫子』は抽象的だが、『戦争論』は具体的で理路整然としている。『孫子』は平易な文体で短いが、『戦争論』はドイツ観念論の流れを汲んで難解な文体で、しかも長文である。
内容的にも「戦わずして人の兵を屈する」ことを「善の善なるものなり」と述べる『孫子』と、決戦をもいとわない『戦争論』、情報重視の『孫子』と、「戦場の霧」のように情報軽視の『戦争論』、兵数の大小に関する記述の違いなど相違点が多々見られる。
このため『孫子』と『戦争論』の整合性をどのように見ていくかが、研究者のみならず戦略を立案する人にとって懸案であった。
マイケル・ハンデルは『戦争の達人たち』の中で『孫子』と『戦争論』、それにジョミニの『戦争概論』の相違はおのおのの視点の位置の違いと見なしている。
「孫子が主として、最も高い戦略レベルにおける戦争の追考に関心を示しているのに対して、クラウゼヴィッツは、より低いレベルの戦略/作戦的な戦闘に焦点を当てている」。
『孫子』が外交戦略や政治的取引までも範疇に入れているのに対しクラウゼヴィッツは純粋に軍事問題に絞っている。『孫子』は国家レベル、政治指導の視点まで加味しているのに対し、『戦争論』はより戦場という現場での視点が中心となっている。
このハンデルの視点に対し、平清盛の「平治の乱」の鎮圧も『孫子』と『戦争論』の整合性をより具体的に現実世界で立証したものである。では「平治の乱」はどのような形で展開して鎮圧されたのだろうか。
手勢15名にまで追い込まれた清盛
平治元年(1159年)12月9日、時の権力者・信西入道に反感を抱いていた藤原信頼と源義朝は、信西と協調していた平清盛とその一族がわずかな人数で熊野詣でに出かけて平安京を留守にしている虚を衝いて、叛乱を開始する。
9日の夜、信頼と義朝その勢500余騎が三条烏丸にあった院の御所・三条殿を奇襲、御所に火を放ち、後白河上皇及び上皇の姉である上西門院を内裏の東側にある一本御書所に幽閉した。
同じ頃、信西入道の宿所がある姉小路西洞院へ押し寄せて火を掛ける。13日、信西は奈良(近江方面ともされる)への逃亡中に地中に潜伏している所を発見され首をはねられた。
次いで内裏を占拠した信頼・義朝らは二条天皇を清涼殿の北側にある黒戸の御所に押し込める。そしてお手盛りの除目を開始する。信頼は右近衛大将、義朝は播磨守になり、味方した貴族へも官位を濫発する。
熊野参詣の途上にあった清盛のもとに叛乱の報告が届いたのは乱勃発の翌日10日のことである。
このあたりの詳細は『平治物語』と『愚管抄』で若干、差異はあるが、総勢は息子の重盛(いなかったという説もある)、基盛、宗盛などわずか15人足らず、清盛はいったん西国に落ちて勢力の増大を図ることまで考えた。これは敵の勢力圏から離脱し、味方の勢力圏にて力を回復する方法である。
しかし、清盛は在地武士の湯浅権守宗重や熊野別当湛快の援助で何とか兵を調える。こうして清盛は最初に軍事力を確立した。
この段階での清盛の行動は、情報を収集し、可能な限り確実なデータに基づき、複数の目標(西国か平安京か)をもちながらもおのおのにリスク計算をし、最終的な方向性を己の軍事力と敵の軍事力の客観的な差により決定するものであった。
ここで「可能性の技術」としての戦略は「ゲームの理論」的に形成されていることがわかる。そのうえで敵の待ちかまえる平安京に上洛する。
これは『孫子』でいう兵を「死地」に入れたことになる。